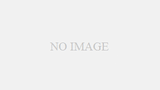【魏志倭人伝の解読における論理的思考法】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGX5TGKS
はしがき
魏志倭人伝は、従来の思考法では解読が困難であり、定説が未だに確立されていないことがその証左である。解読における従来の思考法は、文献の歴史的背景の理解を重視し、同時期の史料と比較して相互に補完するよう考察する。また、考古学的証拠を不可欠な要素として重視し、国名の発音に着目して場所の比定作業を行う。これが、倭人伝解読における論理的思考法として広く認知されている。
しかし、これらは解読における二次段階のアプローチであり、一次段階の文書の読解が完了してから行うものである。倭人伝の翻訳文は、ほぼ全てが、日本語の文章として不完全であり、一読して内容が理解できるものはない。原文に書かれていることを十分に理解して翻訳されたものではないからである。ゆえに、不完全な翻訳文に基づき、二次資料を用いた二次段階のアプローチが行われることになるが、この思考は論理的ではない。
不完全な翻訳文は、既にそれ自体が間違いを含んでいることを理解しなければならない。
正攻法こそが論理的思考法である。一次資料である倭人伝の一次的な読解を、正しい日本語の翻訳文にできるまで、諦めずに追求することが正攻法である。
そして、その読解は、二次資料の情報をできるだけ排除したものでなければならない。二次資料の情報に左右される一次段階の読解など、本来の翻訳作業とは言えない。そのような翻訳作業で得られる日本語の文章は、もはや倭人伝の翻訳文ではないのである。二次資料への依存を排除し、文書の読解に集中した正攻法のアプローチにより、従来とは異なる真の魏志倭人伝を理解することが可能となる。
二次資料を排除して文書の読解に集中するアプローチは、倭人伝をフィクションとして扱うかのようであり、従来の研究者には稚拙で心許ない手法に映るかもしれない。しかし、まずは書かれている物語を正確に読み、正しく理解することを優先しなければならない。
倭人伝は、読めば読むほど違和感を覚え、読めば読むほど著者の意思を強く感じる文書である。この感覚に至るまで何度も読み込む者は、そう多くはないだろう。それができるのは、著者または編纂者の陳寿を信じる者だけである。どんなに専門的な知識があっても、数回読んだだけで翻訳文を完成させ、すぐに二次資料を参照する者には、倭人伝を解読することはできないと歴史が証明している。
信じて諦めずに何度も繰り返し読むことで、「読書百遍、意自ずから通ず」の言葉通り、陳寿の意思と倭人伝の構造がおぼろげながら見えてくる。
京都大学名誉教授の牧健二先生は、論文「原文に忠実な魏志倭人伝の解読:後漢書の倭国観の誤謬(ごびゅう)を重点とする研究」のはしがきに次のように書いておられる。
「倭人伝には、たとい事実の記載に誇張があり、何程か日本の地理の実状に合わないところがあるとしても、文章そのものは読めないものではあるまいし、その内容も不可解なものではあるまい。方角でも距離でも原文の文字どおりに読んで、筋のとおった第三世紀の倭人の国土と社会との叙述に接することのできる史料であろう。倭人伝を忠実に原文の意味を捉えることができるように読む解読の途はどこに在るのであろうか。」
この見解に対し、全くの同意を示す次第である。魏志倭人伝を読み解くには、この考え方が必須であろう。本研究は、この見解の最後の問いに正面から回答するものである。