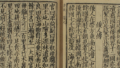魏志倭人伝の固有名詞はどう読むべきか
はじめに
『魏志倭人伝』は、中国の三国時代に編纂された『三国志』の一部であり、倭(古代日本)についての貴重な記録が記されています。この文献は、日本古代史の研究において重要な資料となっています。しかし、ここに記載されている固有名詞の読み方については、多くの議論があります。特に、これらの固有名詞をどの時代の発音で読むべきかが重要な論点です。この記事では、『魏志倭人伝』の固有名詞をどのように読むべきかについて考察します。
上古漢語と中古漢語の違い
まず、上古漢語と中古漢語の違いを理解することが重要です。
上古漢語
- 時代: 紀元前1200年頃から紀元3世紀頃まで。
- 音韻体系: 上古漢語の音韻体系は複雑で、多くの声母(子音)や韻母(母音)を持っていました。声調は未発達で、高低差程度のものとされています。
- 主要資料: 甲骨文字、金文、『詩経』、古代の漢詩、春秋戦国時代の文献など。
中古漢語
- 時代: 紀元3世紀から10世紀頃まで(南北朝時代から唐代)。
- 音韻体系: 中古漢語の音韻体系は簡略化され、現代中国語に近いものとなりました。四声(平声、上声、去声、入声)の体系が確立されました。
- 主要資料: 韻書(『切韻』、『広韻』など)、唐詩、仏教経典など。
魏志倭人伝の時代背景
陳寿は西晋の時代に『三國志』を完成させました。正確な完成年は不明ですが、おそらく280年頃から290年頃にかけて編纂が行われたと考えられています。この時期は、上古漢語から中古漢語への過渡期にあたります。したがって、『魏志倭人伝』の記述は、中古漢語の初期の発音を反映していると考えられます。
固有名詞の読み方
『魏志倭人伝』に記載されている固有名詞の読み方について、中古漢語の発音に基づくべき理由を考察します。
1. 時代の一致
『魏志倭人伝』が編纂された時期は、中古漢語の時代にあたります。このため、文献の記述を当時の発音で読むことが、原文の理解に最も適しています。
2. 韻書による再構築
中古漢語の発音は、『切韻』や『広韻』といった韻書によって詳細に再構築されています。これにより、当時の発音を比較的正確に再現することが可能です。上古漢語の発音は再構築が困難であるため、中古漢語の発音に頼ることが現実的です。
3. 言語変化の理解
上古漢語から中古漢語への変化は、音韻体系の簡略化や声調の確立を伴います。これにより、『魏志倭人伝』の発音を中古漢語で再現することで、当時の言語変化の過程を理解する手助けとなります。
4. 日本古代史の研究
『魏志倭人伝』は日本古代史の研究において重要な資料です。当時の中国と倭の関係や、倭の国々の状況を理解するためには、文献を可能な限り正確に解釈する必要があります。中古漢語の発音を用いることで、当時の実情をより正確に把握することができます。
具体的な固有名詞の発音
以下に、『魏志倭人伝』に記載されている主な固有名詞の中古漢語の発音を示します。
-
狗邪韓国(くやかんこく)
- 狗邪韓(gǒu xié hán):kuw3 d͡zja2 han2(クゥ ザ ハン)
-
対海国(たいかいこく)
- 対海(duì hǎi):tuwi4 xoi3(トゥイ ホイ)
-
一大国(いちだいこく)
- 一大(yī dà):ʔit8 dai6(イッ タイ)
-
末盧国(まつろこく)
- 末盧(mò lú):mat8 luo2(マッ ルオ)
-
伊都国(いとこく)
- 伊都(yī dū):ʔi1 tu1(イ トゥ)
-
奴国(ぬこく)
- 奴(nú):nu2(ヌ)
-
不彌国(ふみこく)
- 不彌(bù mí):put8 mi2(プッ ミ)
-
投馬国(とうまこく)
- 投馬(tóu mǎ):duw7 ma3(ドゥ マ)
-
邪馬壹国(やまいちこく)
- 邪馬壹(xié mǎ yī):d͡zja2 ma3 ʔit8(ジャ マ イッ)
-
狗奴国(くぬこく)
- 狗奴(gǒu nú):kuw3 nu2(クゥ ヌ)
-
卑彌呼(ひみこ)
- 卑彌呼(bēi mí hū):pi1 mi2 hu1(ピ ミ フゥ)
-
卑彌弓呼(ひみくこ)
- 卑彌弓呼(bēi mí gōng hū):pi1 mi2 kjuwng1 hu1(ピ ミ キュウン フゥ)
-
難升米(なんしょうまい)
- 難升米(nán shēng mǐ):nan2 shyeng1 mi3(ナン シェン ミ)
結論
『魏志倭人伝』の固有名詞を読む際には、中古漢語の発音を用いることが最も適しています。これは、文献が編纂された時期の言語体系を反映しており、当時の発音を再現するための最も現実的な方法です。日本古代史の研究においても、原文の正確な理解が求められるため、中古漢語の発音を基にした読み方が推奨されます。
これにより、『魏志倭人伝』の記述がより正確に解釈され、当時の中国と倭の関係や、倭の国々の実情を深く理解することができるでしょう。
解説
お気づきかもしれませんが、結論までは ChatGPT 4o に書いてもらいました。
疑問点を質問しながら対話を繰り返すことにより、最終的なまとめをしてもらったのです。
この文章を読むと、魏志倭人伝の固有名詞の発音を「倭人が発した言葉」とする解釈が、必ずしも正しいとは言えないと思いませんか。
であるならば、そうではない解釈もしなくてはならないと思います。
それが、解読の方針「漢字の意味で読む」なのです。