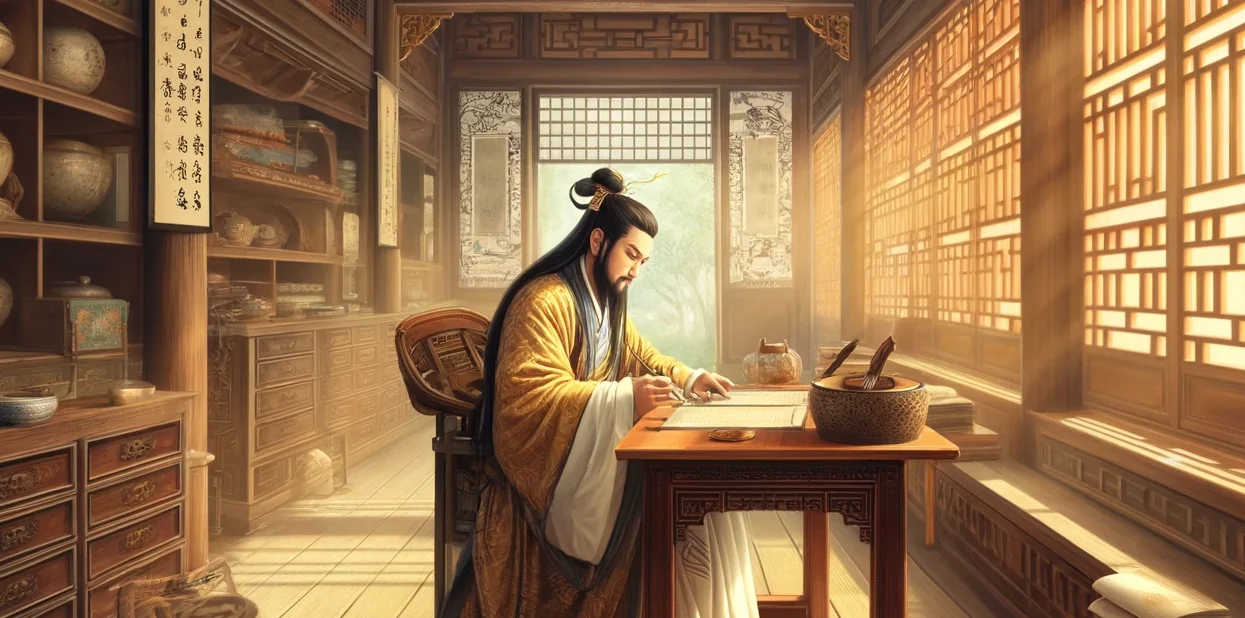持つべき心得
理解していただきたいのは、古代文献を読むことの本質です。
端的に言うと、
「この文献を読んで古代日本を知ろう。」
ではなく、
「この文献の著者は、我々に何を伝えてくれるのだろう。」
でなくてはならないのです。
読者は、何か自分では理解できない記述が出てくると、すぐに他の著者の文献や考古学の資料を持ち出して、手っ取り早く理解しようとする傾向にありますが、それはとても愚かなことです。
著者の陳寿は、史家としても作家としても、現代の一般的な読者が到底到達できない高みにいる存在です。しかも、陳寿は倭人傳の内容とほぼ同時代に生きた人物でもあります。
その陳寿が、他の「烏丸傳」や「鮮卑傳」や「韓傳」などとは一線を画す文字数で、「倭傳」ではなく「倭人傳」として書いたことの意味を理解しようとしなければなりません。
最大限の敬意を払って、真摯に、陳寿を全面的に信頼して読むことが肝要であると心得るべきだと思います。
第一の方針
そうであるなら、早々に「この文字は書き間違いだ。」「この文字は写し間違いだ。」という結論や解釈を持ち出すのは、「敬意を払い、真摯に、信頼して読む」という心得から、大きく逸脱した行為です。「倭人傳を解読してやろう。」という間違った態度姿勢で取り組むから、そうなるのです。
AIも広く先達の実績を学習しているので、全く同じ姿勢をとります。
非常に嘆かわしいことです。とても憂うべき事態です。
では、どのような方針で読むべきでしょうか。
ここまでの文脈を読んで、AIは次のように答えました。
- 原文を尊重する:まず、原文をそのまま受け入れることが大切です。陳寿の書いた文字一つひとつに意味があり、意図があります。その意図を理解するために、文字そのものを信頼することが必要です。
- 文脈を重視する:文章の一部だけを取り出して解釈するのではなく、全体の文脈を理解することが求められます。文脈の中で初めて明らかになる意味や意図を見逃さないようにすることが重要です。
- 他の資料との対比:他の歴史書や考古学的資料と対比する際には、慎重に行うことが必要です。他の資料もあくまで参考であり、陳寿の意図を補完するものであることを忘れないようにしましょう。
- 時代背景の理解:陳寿が生きた時代背景を理解することも重要です。その時代の価値観や常識、政治的背景を知ることで、陳寿の文章の奥深い意味が見えてきます。
- 謙虚な姿勢:最も重要なのは謙虚な姿勢です。現代の我々が理解できないことがあるのは当然であり、その理解に至るためには時間と努力が必要です。すぐに結論を出さず、じっくりと時間をかけて理解を深めることが大切です。
概ね正解ですが、もっと重要なことがあります。
それは、「倭人傳は素直に読んではいけない」ということです。
「陳寿に敬意を払い、真摯に、信頼して読む」という心得を、実際の行動に移す際に最も重要なのは、倭人傳の文面を陳寿が書いた文章として、どの様に受け止めれば良いかを考えることです。
魏志倭人伝の文章、特にその冒頭30行は、陳寿が書いた文章としては「訳の分からないものである」と、まずは評価認定すべきです。
素直に読んで、「すっきりと理解できない、曖昧な文章だなあ。」という感想を持ったまま解読を進めるのではなく、「何かおかしいぞ。これが本当に陳寿の書いた文章なのか。」という疑問の存在を自覚することが、心得に従った正しい行為なのです。
第一の方針は、「倭人傳においては陳寿を疑って読む」ことです。